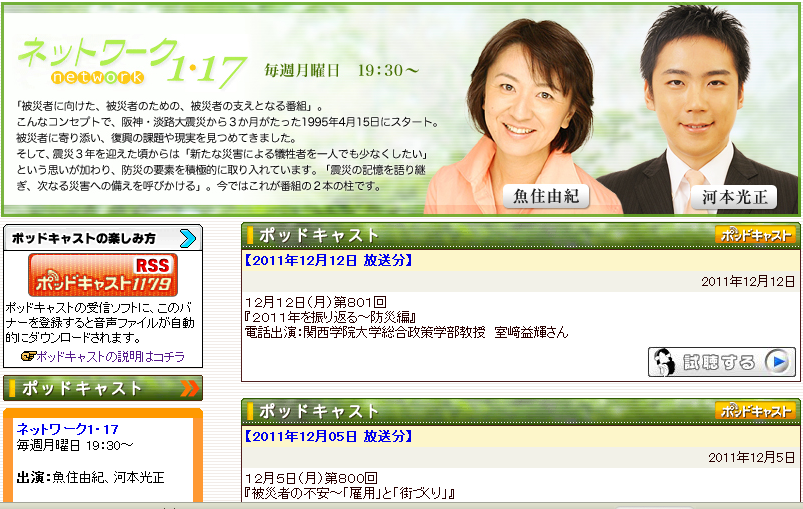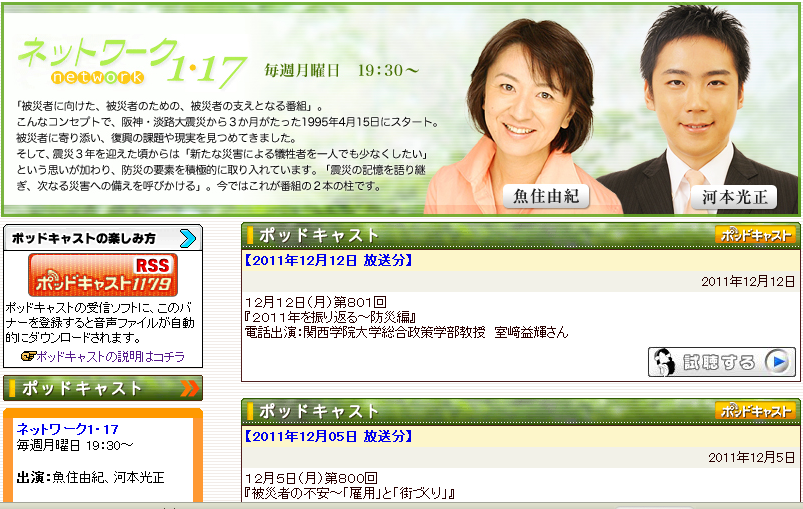さて先日、「Jimdo Founder’s Camp ~あおによし in 東大寺~」というセミナーイベントにいってまいりました。HPはこちらから!
みなさんはご存知でしょうか、jimdoというものを。
簡潔にいえば、ホームページを誰にでも簡単に作れるサービス!コンセプトは「Pages to the People!」
これはもうとにかくシンプルかつイージー!彼らの言葉を借りるなら
「No more HTML, No more CSS, No more FTP, No more Skill」。これはやってみなくちゃわからない快感さです。
ドイツ生まれのどんどん成長している、現在は世界で500万ユーザー以上のイケイケな会社。もっと知りたい方はこちらから!
日本ではKDDIと組んでやっています。最近では「みんなのビジネスオンライン」という企画でGoogleと提携したりもしています。
この創業者が来日して奈良でセミナーを開くというのだから行くしかないということで、一時間ほど電車に揺られて鹿であふれる奈良公園へ行ったのでした。プレゼンに使われたスライドはメールでいただけるということで楽しみ。その前に、当日きいたことを自分でまとめておこうと思います。
①Jimdo JAPANのカントリーマネージャー駒井氏のお話

jimdoの概要を説明されていました。イケメン!
利用者はほぼ個人事業主含む中小企業。アーティストも多数使用しているそう。
あの超人気アイドルひかたろうのHPもjimdoですね!(宣伝ですけど)
彼のメッセージは「jimdoはホームページを簡単に作れるからといって、それがすなわちいいホームページになるとは限らない」ということ。いいホームページとは?という部分を考えさせる今回のセミナーの導入となるプレゼンでした。
②コミュニケーション研究所 竹林氏のお話

ホームページで伝えるべき事を考えるときに、マーケティングの考え方をベースにするといいというお話。
何をどう伝えるかというのは、ホームページ上では”何を”→テキスト、”どう”→デザイン で表現し、考えるにあたってはMarketing →Message →Designと落とし込んでくればよいということです。
マーケティングの戦略で秀逸な企業の例として、かの「鳥貴族」を紹介されていました。
各項目での鳥貴族のケースは右に書いていきます。
・ビジネスモデル(誰に?何を?) →若い人に良いものを
・コンセプト →「生活必需店」
・セグメンテーション、ターゲティング(絞り込み) → 居酒屋>焼き鳥>低価格
・ポジショニング(位置取り) →ボリューム、明るい雰囲気
・ストレングス(強み)→安い、早い
なるほどよく考えてるなという感じです。
そしていわゆるマーケティング4Pも、ここでは割愛しますが、シンプルに考えられていて、それがうまいこと鳥貴族HPに載せられていました。
ここで大事なのは、重要なこと・本当に伝えるべきところだけを発信すること。「本当に伝えるべきこと」を明示するということは「お客様にとっての価値」を明確にすることである、ということです!
「Jimdo もったいないを救え」と題し、ビジネスでJimdoを活用するにあたっての考え方・テクニックを伝授していただきました。jimdoだけの話ではなく、HP制作/運用全般にも言える事なので、非常に勉強になりました。
まずはページ作りに関して。
・テキスト →文字サイズは大きめ、行間は広め
・画像 →ヘッダー画像で印象付ける!コンテンツ内の画像は文章を補うものとして使う
・見出し →見やすさとともにSEO的にも有効。要約や結論にするとよい
・階層 →ページの整理としてメニューに
運用の考え方に関して。
・ホームページの目的は?
→ビジネスで使う場合は「売上につなげること」。HPでは商品・サービスをプラスマイナスゼロで伝えることが大事(誇張して伝えても次につながらないから)
・お客さんの行動
→お客さんの視点に立ち、その行動を予測する。どのページをどういう順番で見るか、どういう情報を求めているか。場所・営業時間・連絡先・申込方法など、お客さんとの接点となる情報は必ず忘れない。
印象に残ったのは「ホームページをもつのは、お店を構えるのとおなじ」ということば。アクセス解析なども活用して、うまく運営していこうというお話でした。
④Jimdo創業者の3人(Matthias Hentze、Fridtjof Detzner、Christian Springub)のお話

タイトルは「Being successful with your website」。既存のお客さん、新規のお客さんとjimdoのホームページでどうつながっていくかというお話。英語でペラペラと話してらっしゃって、なんとちょっと眠くなっちゃって記憶があいまい!スライドをもらえることを楽しみに待っておこう!
肝心なところはブログには書かないぜ!っていうことにしておきます。
しかし仲良さそうやったなぁこの3人。
このあともjimdo新機能の説明や、質問会などありました。
とってもいい経験でした。
ここまでjimdoのまわしもんかのような絶賛を繰り返しておきながら、まだあんまりちゃんと使った事はないんですけどね。有料版を使えば割とマジなビジネスサイトが一瞬で作れるこのサービス、みなさんもいかがでしょうか。